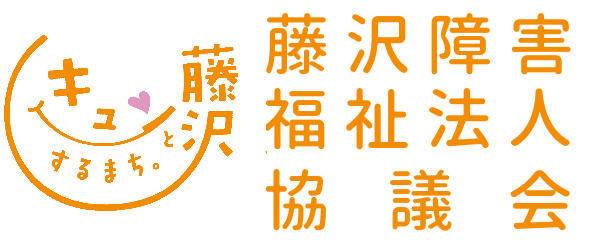障害福祉法人協議会の黎明期
本谷 ありがとうございました。石渡先生には身近な藤沢のことをとらえてお話ししていただき、全国との違いをおっしゃっていただけたかなと思いました。3法人の特徴が、地域作業所からが始まっているんだということを五十嵐代表に、お話しいただけたらなと思います。
五十嵐 いくつか、柱はあると思うんですけれども、とにかく3法人でこの協議会を立ち上げた当時のわたくし自身が感じていた背景と、自分たちがやっていた運動・行動について、申し上げますと、今まさに進行役が言われました通り、あの当時藤沢住んでいたという当事者たちがというふうに石渡先生からもおっしゃっていただいたのですけれども、それは逆に何にもなかったから無我夢中でみんながかなり必死に動いていたという時代でした。
あの当時昭和54 年に小中学校義務化の問題と重度の障害を持つ人の生活をどうするかというところから始まった。でも学校が高等部までの人なら高等学校まで行くのが当たり前じゃないか。ということなのに、障害を持ったがゆえに、まして重度の障害だったゆえに、高等学校までいけないのはどういうことだ、ということで白浜養護学校を作っていただいたわけです。
それからそういう中で高等部まで出られても、今度は学校は出たけれど、もう行き場がないという、それこそ本当に切実な実態がありましたから、それをなんとかしていかなきゃいけないということを考えながら、私たちも自分たちの活動をしていました。まず地域作業所の制度をつくって、当時は県知事が長洲一二さんだったものですから、比較的すぐにOKしてくださって、地域作業所を星の数ほど作りましょうと約束してくださった。初年度は11 ヶ所くらいできたんですけど、わたしたちもその中に入って、真っ先に始めたということで、みなさんもどんどんはいってきていただいて、比較的早い時期に江ノ島で、神奈川県下の地域作業所の集まりをやりました。
その当時から、とにかく障害福祉法人法人協議会は作りたい、という思いは持ち始めていました。石渡先生にお話いただいたように、わたしたちは、身体障害者が中心。あの当時は法律が全部分かれていましたから、身体障害者でもうちの場合は視覚障害者という当事者で、他にも聴覚から肢体からいろんな身体のジャンルがあるわけですが、視覚障害者が中心でした。
今それぞれの自己紹介を聞いていると、知的障害分野では、戸髙さんも星の村に関わっていたし、小林さんもそうだし、それからみらい社が出てきて、マロニエ会の齊藤さんも、その当時は私より1期先に市会議員になられた西條さんの影響が藤沢では大きかった。
で私はその4年後に市会議員に入って行きました。五十嵐光雄とのパートナーとしての生活を送っているなかで、また光男が盲学校の進路指導をやっていたなかで、学校を出ての問題を解決しなきゃいけないというところで、身体障害の分野に入っていった。それが実態だというふうに思います。
それでこの協議会の基を作るのも身体障害者は光友会。知的障害のほうを育成会さん。それからマロニエ会さんは、ジャンルとすれば身体障害に入るのですが、重度障害の分野と全部それぞれがバラバラでやっていたのでは、ただでさえ高齢者や児童に比べてマイノリティの世界なのに、もっと力が小さくなってしまうと心配しました。そうすると、運動もなかなか実りある運動ができないんじゃないかということを危惧しまして、とにかく力を合わせられるところは合わせましょう、みんなで共同してやりましょうということが発端で、よく集まり、話しました。
1995 年ごろから集まってとにかく若い職員さんが、熱心に集まっていただいて、それで会の発足につながったというのが、実態だと思っています。五十嵐光雄が書いたのと私自身が書いた小論集を2つ引っ張りだして読んでいたんですけれども、 1986 年そのときに厚生省は在宅福祉元年というふうに公言したとあります。
五十嵐光雄はそういうふうな書き方をしています。福祉元年のときは、障害者にも基礎年金ほしいよという運動でした。高齢者はみんな定年になればあるんだけれども、子どもの頃からの障害者には一生年金がないじゃないか、おかしいよ、ヨーロッパではすでにやってるんだからという運動を国のほうにしてまして、やっと実施していただけるようになって。それで福祉元年と表明されたんですよ国のほうは。
でもそのとき五十嵐は書いていますけれど、障害年金は老齢年金額に比べても非常に少ないし、とにかく62,500 円、月額ですね。それだけは障害者年金として誕生したんだけれども、不足である。制度を作ったけれども中途半端、という事案がどんどん具体的に見えてくるなかで、協議会として少しでも大きい声にして国に届けていきたいという、そういう趣旨でみんなで集まって、出発しました。
まもなくして「ひばり」さんが入り、「ひまわり」さんが入り、それからそのあと「エール」さんが入り、「創」さんが入って、「県央福祉会」とういう形で今8法人協議会として8法人で構成され、様々な活動をいまでも続けています。
でもさっきもこの古い資料を読んでいて、肉体的にもとにかく動かなきゃいけないということで大変ではありましたけれども、まだこれからやればできるんだ、やれば広がっていくんだという夢をもって、みんなが頑張っていました。でも正直いって、介護保険法ができ、障害者の自立支援法ができ、それから障害者総合支援法ができ、様々な制度改正というか、近年様々なかたちで、非常に制約を受けて、なにか言っても無駄だなみたいな閉塞感が少しずつ出てきて、なかなか思うような活動が、つまり、ないものを広げていくという活動がいまはできていないと思います。しかし、いまある制度のなかで、こういうことをもう少し広げてほしい、あるいはこういうことをもうちょっと変えてほしいだとか。そうした運動はずっとこれまでも続けてまいりましたから、そんな中で、この協議会が出来ていることは、全国的にも自慢できることと思います。
たままた司会者が新横浜であったつい最近全国身体障害者協議会の研修に行ったときの報告で、群馬県の渋川で、まさに同じようなことをやりだしていることがわかって、今更ながら20 年先をよんでやってきたことを、具体的な事例を含めて自慢できる協議会だなと改めて私は思っています。
本谷 20 年前の時代背景から現在に至るお話で、非常に勉強になりました。当時のことを、齊藤さんからお話ください。
齊藤 そうですね、私は育成会がはじめた星の村というところからなんですが、そもそも親の会が星の村をはじめようという構想は、実際は先ほどの話で白浜養護ができて、太陽の家ができて、というのは念願叶ったのですけれども。 早速いっぱいになって、次の年から行き場のないひとがどんどん溢れ出るという状況がありました。そこで親の会が、親子で楽しんで借りていた畑があって、そこで地主さんの好意もあって、使わせていただいたと。そこが中心なんですが、浜見山のポンプ場の近くに市が土地を用
意してくれたのがあってそこにプレハブとかをもっていって作業所にしようという計画が進んでいたのが、あの当時、ポンプ場は近くにあるし保育園は近くにあるしということで、近くの住民の方々に説明会をしなきゃいけない。説明会をするにあたって、地元の議員さんに根回しお願いしますってお願いしたんですよ。
そしたらちょうど選挙の1年前だったんで、周ってみたら、住民の反対意見がすごいあったらしくて、我々の味方で回ってくれたはずの先生が、説明会の当日にそんなもんあったら困るよと。(笑)どうしちゃったんだろうというところから始まりました。
我々を応援してくれた民生委員の方もいれば、そんなもんできちゃ困るという反対運動に署名した民生委員までいてね、そらいかんという民生委員が反対する署名をしてまわったり、地域が荒れに荒れちゃったんです。結局建たないねっていう話になってそこは諦めて、地主さんのご好意でその畑のなかに建物建てるということになったので、1年なにも建物もないかたちで辻堂市民センターを朝借りて、畑に行って、お弁当食べて、帰るという生活をしていました。
その間も畑にパラソルが1枚しかなくてですね、そこが作業所、という形でやってました。幸い、建物が建ってから、いろんなことが始められてやっぱり作業所といってもたんに作業するだけじゃなくて、藤沢のもともとの土壌があったところですけれども、住民運動が結構さかんな土地なんですよね。ゴミのことをやっている方とか、自然食をやっている方とか、いろんな方々が応援をしてくださいました。星の村で作った野菜も、無農薬で有機農法で作って、そういうグループの方々にお分けしたりとか。農福連携じゃないですけれど、その原型みたいなところがすでに芽生えていたのかなというところがあります。
畑に向かない人もいますので、機織りの先生が見つかったら機織りをやって、それぞれ作業を開発しながら作業所もニーズに合わせて、最大4つに増えていったという経過があります。先ほどのお話のように、育成会の法人化をしたりして、マロニエ会も法人化して、だんだんこう基盤を固めていかなきゃいけなくなったと。市内の社会福祉法人化3つめのところで、さっき言いましたようにうちの伊澤潔理事長が、「五十嵐先生教えてくださいって」ということで門戸を叩かせていただいたのが、定期的な交流が始まるきっかけにはなったのかなと思ってます。
障害者プランが国で出されあとに、藤沢版を作らなきゃいけないということで、当時、各法人の課長レベル位の職員が集まってプロジェクトができました。
五十嵐 一つだけ付け加えておくと、白浜養護学校のことも太陽の家のこともそうですけれども、当時、葉山市長のご兄弟のお子さんに重度の障害を持った方がおられたということも、わたしたちの藤沢の障害福祉諸施策のひとつの特徴を作り出す礎になっているかなと私は思いました。
小林 齊藤さんがお話しされた、星の村の作業所の最初期は知らないんです。わたしそのころから3年目くらい、81 年ですか、すでにプレハブが建ってた。でも畑のなかにプレハブ1個だけというときでした。私が81 年に入ったころには、すでに初期のころの話は伝説化されていて(笑)、最初はパラソル一本だったよという話をまず最初に齊藤さんから聞かされたのをよく覚えていますけれども。なので苦労したんだな、と。
齊藤 当時星の村で、家に引きこもっている3人がいたんですよ、その3人をまず引っ張り出したいんだというところからモチベーションが上がっていきました。とにかく、なにをやっても出てこなかった人がいたんですけれど、当時の会長が、お願いに行って、星の村というのを作るんだけど、村長さんをお願いできないかしらって、その方にお願いした。そしたら 村長だったら考える、という返事をもらって、それで、村長として出てくる。その村長さんとすごく仲のいいお友達がいて、その人も引きこもっちゃったんだけど、その人も助役さんということで来ていただいて。
小林 もうね、亡くなっちゃったけどね。その二人は、私は縁としては、私の実の兄が、知的障害でずっとお世話になった親の会で、今話に出た2人とは同級生でした。そういう年代だったんですね。だから、そういう縁もあって、西條さんに紹介されたっていうのもあって、お世話になりだしたんですけれど。そういう最初のつながりがね、育成会としての作業所として仲間でした。
サービスと言われだしたときは、すごく違和感があった。そういう感じ、君付けでいこう、ということでお互い君付けだった。職員も、利用者から、私は小林くんです、齊藤くんです、みたいに。そういう時代でしたよね。
本谷 戸髙さんも引き続き話がありますか。
戸髙 精神の場合はさっき言ったように、保健所とひまわりが一緒にやるみたいなところがずっとあって、その辺がベースにありました。もう一つのキーが、ふれあいセンター。あの当時1980 年代に、3障害があそこに知的身体精神自閉の預かりとケアホームができると。あのふれあいセンターが一つのキーで、うちはあそこのなかに入るという事で、一時的に県の施設を借りたんですけれども、暫定でふれあいセンターに入るんだよということだったんですが、そこのなかで、家族のところと障害団体が一緒に集まるという、ふれあいセンターを作るために6団体が集まって、そこにひまわりも入りました。地域のああいう障害を超えた連絡会ができたっていう例は、多分なかったですよね。ふれあいセンターができたことで、うちなんかもそこに仲間にして入れてもらって。
ほんとにうちはふれあいセンターに入るときも、地域から反対があって、ひまわりだけ入るなと。その時も、検討会の一番最後に、あそこの自治会から、ひまわりは入るなと言われて、役所の職員もだめだと思っていたのが、市長が出て、何言ってんだ、ふれあいのなかにひまわりが入らなかったら、ふれあいじゃないだろう、って。組長がそこでゴー出したんで、市の職員が、その当時の課長さんと夜、農家の人がいる時を狙って、足しげく通って、最終的には反対の方がうちなんかに来たんですね。
その当時、川崎のあやめっていうところが建物立てて3年入れなくて、鎌倉は佐助のところで夏と 冬と作業閉めなきゃいけない。そういうところで 反対運動があって。川崎は 駅から送迎をすると。反対の人が来た時に課長にちょろっと送迎の話が出たんですね。送迎するんだろうみたいな話で、最終的にやらなかったんですけれど、ふれあいセンターのオープンの時に、餅つきをやっていたら、後ろの方で地元の人が、送迎やるって言ってたけどほんとにやるんかね~と。またそんなこと言って。ほんとにふれあいセンターのなかに、わたしは1986 年から入って あのとき齊藤さんが下に、こ とりがいて、うちが2階で、隣に肢体があって。そこで私は10 年くらいやっていたんですけれども、そんな部分と。あと、ワークショップに仕事を、内田さん? がいたときにいろんな仕事をもらったりとか。本当そういう部分が当たり前に、そんなかんじで。なんか、光友会で精神の勉強するから、って行ったり。そういう往来があった。星の村はあそこでバザーやってたんで、その真似してうちがバザーをやって、そのあと遊行寺でバザーやるとか。なんかそんな、あちこち繋がっていて当たり前。そんな感じがあったんだろうな。
藤沢の場合は精神 例えばグループホーム作るにしても、市の職員が検討会に入って、いろんな関係者が入って、その中に市の担当も入って、一緒にやる。なんか、藤沢の中で精神という場合も、精神を受けていく状況のなかでも、担当がきちっと対応、そういう意味では精神のことに関しては 行政がちゃんとかかわっている というのは、他に聞くとそんなにないかなという感じがするんですけどね。
オアシスができたときも、そのときの部長が久世さんで、あのとき湘南ふくし村のなかに精神のことを入れる義務規定がなかったが入れたんですね。「入れなきゃそんなのができない」とガチっと入れてくれて、精神にとっては行政が、あのときは予防課かな、すごい分かってくれて関わってくれました。多分それは言わせると家族会が本当にしこしこ頑張って、やったみたいなところがあったのかなあと思います。自分のなかでは藤沢では他の障害の人とぜんぜん普通に当たり前に顔が繋がっているみたいなところがあったかなと。
本谷 ありがとうございました。自分からもお話しします。
最初のころ希望の郷は入居施設でしたが、光友会の理念としては「隔離と管理から脱皮する」という地域の入所施設であっても地域福祉の拠点になる事。地域住民のお互いの顔が見えるようなそういう関係性を持たなきゃいけないと五十嵐光男施設長から言われ、とにかくお祭りがあれば一緒に行こう、カラオケがとても好きですから、お祭り時はだいたい入居者連れて盆踊りの後のカラオケ大会に出るとか、それも御所見地区は、また市民センターでやる以外に、小学校でやる、宮原地区でやる、いろんな地区ごと6地区あるんですがね、近いところへは顔出して、獺郷神社、宮原神社、用田、まあそんなふうに地域に出ました。それから文芸誌も発行できるんじゃないか、入居者で学校の先生をやっていたかたが入って来て「かわうそ文芸」を発行した。入居している人も、自分の持てるものをどう使って外へ出ていくか、地域福祉づくりをしました。また、県外の施設見学もしました。
五十嵐 見学だけじゃなく職員の1 週間ずつくらいの交換研修もやりましたね。
本谷 職員共済会をつくり、積立金をして職員全員がグループ分けして、一泊二日で見学に行くとかしました。先ほど理事長の言われた、群馬県渋川の療護施設「誠光荘」に30 年くらい前に行ったときの職員が現在理事長になって研修後、他に職員さんもいたけれど、一緒に話したり、そういう繋がりが、今も生かされているかなと思います。
石渡先生、こんなお話しを聞きながらどうでしょうか。
石渡 ふれあいセンターって、今どうなっているのですか。
五十嵐 今閉鎖してしまいましたが、市の外郭団体でやったのね。藤沢市民病院のドクターと、看護師さんが住んでたところを使ってできました。
齊藤 ゆうかり園のナースの寮だった。そこを、市が買い上げて。それも最初は育成会がセンターにしたいって市に申し込んで要求をしてたんだけど、市とするといろんな要求を受けてるから、育成会だけってわけにはいかないよって、それでふれあいセンターっていう構想になっていったっていう経過ですね。
石渡 今のお話しを聞いて、反対運動があったみたいな話って、ちょっと、信じられない感じなんだけど。やっぱりあるんだなーということを感じました。さっき君付けで呼び合ってたみたいな話なんかもきいて、福祉っていうと、慈善みたいな、立場の違いが明確で、スタートしているなって思うんだけど、藤沢の場合はそうじゃないんだなっていうのをすごく感じました。それは作業所から始まっているっていうのが大きいんだと思うんですよね。本当にこうおんなじ藤沢に住んでるっていう。
それで、あと面白いなって思ったのが、村長さんや助役さんを作って、いま、こうお世話になる立場ではなく役割を持つみたいなことをさかんに言ってる時代だけど、当たり前にそういうことをやれていたっていう、そういう発想が、今の藤沢を作っているんだなっていうのを感じました。
3障害ではないっていうのが、藤沢のすごく大きな特徴かと思うんですが、ふれあいセンターの存在みたいなのを聞いて、一市民としてみたいな発想から、いろんなことがスタートしてるんだなっていうのを再確認したんですけれどね。あと反対運動をやっているところって、実はあとになると大きな協力者になるみたいな話もよく聞くんですけれど、それもそうなんですかね。
五十嵐 うちはうちで十何年も前だけど、ライフ湘南も同じ、横浜のいそご地域活動ホーム建設も同じくらいに建設に対しすごい反対運動があって、私も何べんも伺って。
うちには娘がいるのにもし万が一のことがあったらどうしてくれるんだと。そういうことは絶対にありませんなんて私は言い切れませんとはっきり申し上げました。でもね、もしあっても、最善の方法でとにかく対応しますって言って、じゃあ分かったって言って頂きました。
そして今はいぶきのなかに、植物好きなその方は、観葉植物とかいろいろ持ってきてくれたりしてすごい協力者になってくれてるし、ライフ湘南だって、レストランつくってるから、建設に反対してた人たちもみんな来てくれています。だからとにかく、腹割ってという言い方はおかしいけど、説明してある程度理解してくれたら、そういうもんなんだってわかると、今度は協力者になって強い味方になりますよね。
戸髙 うちもあのとき自治会のトップの方が、協力してくれて。結局うちがあそこからでて隣に行ったんですけれども、もともと地の名士の方がうちの地主さんで、やはりひまわりっていうことで反対するわけでもないですし。
小林 反対の理由は育成会の場合でいうとそんなに表立った感じじゃなかったけどその辺はやっぱり西條さんがきちっと対応してくれました。むしろそれ以降は、歓迎されるか良好な感じで。逆に地域の方が協力以上に頼りにするみたいな形でやらせてもらってますね。
戸髙 一件だけ、ふれあいから出る時に、日大の前あたり、藤沢養護の裏に行く予定で物件探して行ったら、反対やられて、自治会に話をしに行ったら、すごい反対で。さっきのはなしじゃないけど、うちのこどもがいるとかなんとかの話で結局は、その一週間くらいしたら、市にひまわり移転反対署名が提出されていました。そのときの職員7、8人連れていったらもう針の筵のわけですね。で、もうそこは無しにしたから今があるんですけれども、そんなことが6年くらい前にありました。
本谷 用田奥に、特別養護老人ホームが昨年2 月にできたんですが、そこで集まりに行ったら、玄関前の家のベランダに、垂れ幕で「建設反対」っていまだに2 カ所ありました。
五十嵐 特養の場合は、霊柩車が頻繁に来るからいやだって。そういう反対の理由が多いみたい。