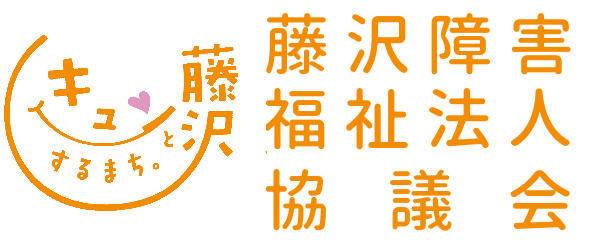活動の原点
本谷 次に、20 年間にわたる協議会の活動になりますが、藤沢障害者プランへの提言作る経緯など齊藤さんからお話ください。
齊藤 実際に各法人で集まって、それぞれの施設の中身の話とか、よくよく聞いてみるとやっぱりお互い知らないのね。その中で最初のうち、本をまとめるどころじゃなくて、情報交換でもものすごい時間がかかったのがいまだに覚えています。いかに自分のなかの施設の中の常識って、周りからみたら非常識なのねっていうのが、よくわかるような体験を最初にしたっていうのがお互いの大きなスタートのような気がしますね。
ちょっと前の話に戻っちゃうけれど、さっきちらっとでた江野さんとか、小林くん、梅村くん、梅田くん。戸髙とか私とかそういうのがね、松ぼっくりの市民会議という名前を付けて、ボランティアグループをやってたんですよ。毎年夏の合宿なんかもやって、相模緑風園の藤沢在住の十何人の方が 2週間くらいお家に帰ってくるときに、ずっとお家にいると、お母さんもへたばっちゃうんでね、2泊3日しかないんですけれど、合宿をしようっていうんで、聖園の記念館というところに借りられるところがあって、2泊3日でお風呂に入ってご飯を食べて楽しいことして、最後、男性ボランティアがみんなで女装して踊ったり バカ騒ぎをして思い出を持って帰ってもらうという、それもう15 年くらい続けた。
仕事になっちゃっても、みんな各職場から集まってね、そんな活動を続けて。そんな仲間が基本にあるのかな、というのはあります。その世界とはちょっと違う、五十嵐先生を中心としたグループとか。それが融合したのが、スタートですね。
本谷 そうですね。今日集まっている方々は学校出てから企業に勤めたり、「福祉」を知らないまま「福祉」の仕事に就いた。また20代で会社を辞めてボランティアしたりとしても食べていくために福祉に入ってきたことが、お金を得るということもあった。
光友会の創設者から福祉に携わった事を聞くと消極的にやっちゃいけないな、障害を理解していただくということでは、もっともっと外に出て一緒になって運動していかないと、当事者が一番生きづらい思いをしている。そういう意味でも自分は勉強していこうと思いました。
職場では介護の仕事ですが、入居者と飲み会に行くことも大事だなと。横浜の職場では、職員はボランティアやってはいけないことになってましたけど、希望の郷は、入居者と一緒に外出し、いろいろなことを教わりました。
苦情解決システム「ポッポNOバリア」の設置
本谷 そんなことから、みんなの燃えるものが結びついて、「ポッポNOバリア」という当事者サイドで苦情解決システムを作ろうということがありました。小林さんから、少しお話しいただければと思います。
小林 ポッポの前に、作業所に関連して、お話したいことがあります。やっぱり五十嵐先生と、西條さんのお力が大きくて、行政、市会議員ということもありますが、当事者である人で議員でやっていたというのが一番大きかったと思います。単なる福祉が分かる議員さんというのと違って、当事者のところから出発している。そこに集まってきたというのは一番大きかったかな。
それぞれが作業所としてやってて、そういう当事者性みたいなものがあるから、そのサービス、与える側と受ける側じゃないよ、というのが当たり前の常識っていうのがありました。あと、それぞれ、マロニエ、光友会、藤沢育成会、ひまわりという各分野で作業所ベースで始まってて、お互いみんな知っててね、作業所連絡会みたいな活動があったから。それが地盤で法人協議会の流れがあったんです。
戸髙 あの頃光雄先生が、障作連の代表になっていたし、障作連の藤沢連絡会をやっていて、お互い知り合ってというところがあって計画にも参加できるようになりましたね。
小林 結果的に作業所から社会福祉法人化になったので、社会福祉法人になってるからそういう立場で集まったのですけど、結局専門分化しているみたいなところがあって、お互いのこと知らなくなってるなっていう時期だったんですよね。
これを見ると、一応3法人だけど、最初の障害者プランへの提言を作るときは、ひまわりの戸高さん、準メンバーでずっと入っていたんですよね。ひまわりは協議会のメンバーではなかったけど、最初から入っている。
戸髙 医療もということで湘南中央病院にも入ってもらいました。
小林 今から考えると、ずっと後の自立支援協議会的な考え方を先駆的にやってたという気はしますよね。
本谷 「ポッポNOバリア」発会式の写真が出てきました。ひばりが加入して4法人になった時に、「苦情解決システムポッポNOバリア」を、4法人が協力して、各法人で第三者委員4人を選んでスタートしました。
五十嵐 あのときも、第三者委員というか、チェック制度を国が作りました。でも自分の法人で1人雇って、お金を出して、自分の法人のことをチェックしてくださいっておかしいよね、っていう話そういう発想で、法人協議会があるんだから、そこで第三者委員制度を作りましょうって、作ったんだよね。
本谷 法人内自己完結じゃない、第三者に申し出ができるシステムとして機能した。光友会でしたら、藤沢育成会の事務局に電話することができるようにしました。
五十嵐 第三者性を持ちながら。利用者さんも、訴えるのに、自分の法人のところにいる委員に伝えるよりは、そういう第三者性を持っている委員のところに直接言えるという仕組みはすごく、あのころすごく喜ばれたんだよね。うちでも、問題を持った人がけっこう直接電話したりして。
小林 第三者委員ね。苦情解決の仕組みそのものが、法制化されたというか義務付けされたから、名前だけつけりゃいいということもあったんだけど、そうじゃないでしょ、ということが出発ですよね。共同でやることによって、客観性を持たせるっていうことを考えました。苦情解決研究会を発足させ2000 年から準備しました。
ネーミングも公募したんです。当事者に、応募用紙作って。当事者の人から、けっこう集まって、選考会やったんですよ。それで、3万だか5万だか出したんですよ。賞金出たんですよ。
本谷 「ポッポ」と「NOバリア」の2つの造語にしたんだよね。
齊藤 それを、選考で合わせちゃおうって。両方マロニエの人だったんだけど。ポッポって一歩一歩って言ってたかな。 そんなイメージの、両方かけてってみたいなこといってましたね。
本谷 そんなことから、第三者委員もそれぞれの法人から選んで、委員になってもらって、巡回をする。
小林 事務局も持ち回りでやっているから、ポッポNOバリアの解決窓口の電話番号は自分のところじゃなくて、別のところの施設になる。自分のところだとちょっとおかしいでしょ、ってことで ポスターやなんかにもそういう風にしてる。
本谷 訪問すると、当事者のかたに、何かあるかって直接お話ししたり、最近だと家族とお話もするってね。
五十嵐 委員のなかには、民生委員さんもいるし、それから弁護士さんもいるし、人権擁護委員さんもいるし、いろいろなプロがはいってくれているからね。