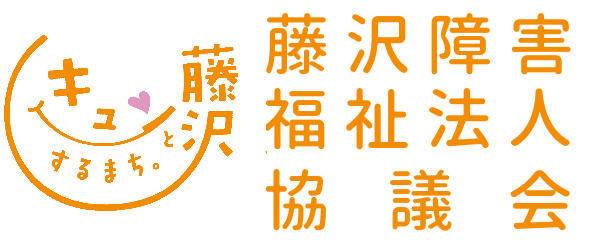行政への要望書と法人協議会としての姿勢
本谷 続きまして、藤沢市障がい福祉施策に関する要望書づくりを齊藤さんからお願いします。
齊藤 要望書を毎年何項目かにわたってつくっていますが、中身のテーマの選び方としては、それぞれの法人が個別で要望したいことは、それぞれでやりましょうという暗黙の了解があって、その法人独自の課題ではない部分、市民目線で考えて、藤沢市としてこれが今必要なんじゃないか、という選び方をして、項目だてをしています。それはもう前から、そういうスタンスでやっているという感じがしています。ただ、今ここが必要っていうのは絶対外さないでいきたいなというのがあるんで、毎年継続テーマももちろんありますが、新しいことが必ず出てくる。
本谷 藤沢市は、地域福祉計画を3年ごとに作っていく。そういうところを先取りしながら、こちらが提言したり、藤沢障害福祉施策の緊急課題を当協議会の総会で、取り決めして市長に持っていく。
小林 事業者団体としての色彩よりも、市民運動的な、あるいは福祉政策を市民の立場で考えるみたいなスタンスはありますよね。だから利益団体ではない。そういう意識はなるべく避けるようにという意識はありますよね。事業者団体だったらそれはそれでやっているところはあるから。
そんな流れもあって、藤沢市の福祉計画委員会とかに以前は法人から決められていたんだけれど、法人協議会から代表でという、そういう枠みたいなのができた、その枠が当たり前に入ってくる。
戸髙 もう6年か8年かくらい前ですよね。最初多分五十嵐さんがこの枠で入ってくるような感じで。多分この辺の流れから、それを我々が要求したんだよね?
本谷 自分達からというより市側から来てくださいっていうそんな動きが出てきた。こちらで講演とシンポジウムをした後必ず報告書を作って、市、市議会、福祉関係団体などに配布する。
石渡 報告書がすばらしいですよという話を齊藤さんとしてたんですけど。
五十嵐 その前に今の続きで一言だけ追加して言うと、要するに藤沢市長がね、今の市長さんもすごく積極的に我々のことを理解されて1年に一度のセレモニーというか、要望書を持って伺った時に話を時間は短くても、聞いてくださるという形をとってくれていて、それは当事者団体というかそういう事業者団体も含めてどのくらいの団体とこういうことをやってらっしゃるのか頭が下がります。
本当に積極的に場所もちゃんと作って待っていてくださって、偉い方達が両副市長も含めて出てきてくださって、話を聞いていただけるということはすごく良いことだし、それからもう1つ、それに関連してるのだけど、私達の協議会にいろんな政策の委員を障がい者関係から出したいから協議会のほうで2人選んでくださいだとか、防災の関係のこういう事も説明したいから協議会のほうでよろしくお願いしますだとか、市がやろうと思ってる事について一応協議会をベースに、どこか1つの事業所、法人とやるのではなくて、そういう形が普通になっているという事がこれも皆が気持ちよく仲良く運動が出来ている1つの大事なポイントだと思うんですよね。
本谷 そうですね、藤沢市の協議会や市社協なんかでも、委員会を立ち上げる時には理事も評議員もこちらから出しているという事で、それぞれの委員として出てますね。それぞれ市だけでなく、市社協にも入ってる。
齊藤 一応各いろんなところに出ていく時に幹事会で全部情報を集約して、まとめた意見を持っていってますから、そういう意味では、「ちゃんとやってくれてるな。」と捉えていただけてるんじゃないかなと思いますね。
五十嵐 それがやっぱり大事だよね。昔のように自分のところだけが受ける形で行政と内緒で話をしてとなってくると、横のつながりというのはなかなかこれだけオープンに気持ちよく出来ないと思うんですよね、継続が。
石渡 そういう行政とのやり取りがあるから、行政が育っているなっていうのはすごく感じますよね。ちょっと他のところではない。
本谷 そうですね、相談事業も先程高齢のほうは先に在宅支援センターができるっていうのはあっても、やはり障害に必要ではないかっていう五十嵐光男さんなんかも厚生省などにずいぶん歩いていって、そういう立ち上げが必要ではないかって、そういうところから当時厚生省の課長さんが来るんですよね藤沢に、それで「どういう相談事業にしたらいいか?」ということから平成8年に身障、知的、精神、3分野でそれぞれ。それで藤沢市が委託事業を始めて、全国で最初ですよね。
相談事業のネットワーク作りも障がい福祉課と3法人が集まってそれが国モデルになりましたよね。障害者自立支援法ができる時に藤沢の取り組みが相談支援事業の国のモデルになった。
石渡 厚労省ともけっこうつながってましたよね、藤沢って。
本谷 全国レベルの委員というと育成会さんからも入っているし、五十嵐光男さんも全国の役員されていたし、戸高さんも、全国レベルで活躍されている。齊藤さんも重心協の事務局の報告書を作ったり。それじゃせっかく報告書があって、先生他、読む人にもこんな取り組みがあったよという話を、齊藤さんからお願いします。
齊藤 最初は、要望書を作り上げる時の作業部会っていう形でやっていたのですけど、会の運営全体を通して幹事会という形でやらせてほしいということで変わってきた。
それとタイミングとしては似たタイミングで障がい者の権利条約の話であるとか、単に要望書のレベルだけじゃなくて、色んな啓発も必要だろうという認識が皆の中に芽生えてきていたものをちょうど小林さんが色々ルート作ってくれて、講演会ができたとか。
その辺から動きがもう1つ厚みが加わったのかなという感じがしますね。ちょっとその辺のくだりを小林さんにお話していただければと思って。
小林 そうですね、背景としては8法人となって比較的規模が大きくなって予算も多少とれるようになったっていう事が1つはあります。研修やっていこうっていうのがあって、法人協議会が比較的予算がとれるようになったんで、東日本大震災の時に法人協議会としてまとまったお金を50 万くらい寄付をさせてもらってるというのがありました。
そういうこともあって、「啓発活動やっていこう。」っていうことで、やっぱり一番その時々の、エポックメーキングというか、福祉の課題は何かなっていう意識でね。ちょうどその時最初の頃、権利条約の発効すぐの時だったんで。やっぱりこの年は権利条約ねってことで。
振り返ってみると、差別解消法になって意思決定支援になって、その時々のつながりがずっとあるんですけど。権利条約だったら長瀬さんかなみたいなところもね。あともう1つあって、必ず当事者の人が入ってる。その分野のスペシャリストと当時者というセットで考えてましたね。
齊藤 この医療と福祉のコラボレーションっていうのは藤沢市が主催でやってたシンポジウムの3回目にあたるんですよね。2回目までは市が主催だったんですけど、総合支援協議会の重度障がい者支援部会でアンケートの報告書を作ったので、これの報告会をやりたいって話をしたんです。
地域包括のほうへ話を持っていって、「こんなテーマでやらない?」って持ち込んで、福祉と医療両方必要な方々もたくさんいらっしゃったので、ちょっとそこコラボレーションするにはどうするの? っていう意味合いでシンポジウムを取り組みましょうって持ち込み企画を持っていったら、「じゃあこれシンポジウムの第3弾にしましょう。」って言って受け取ってくれたんですよ。
その後、第6弾目の「笑顔のために! 相談でつなぐ支援の輪」という「相談」をキーワードにしたものは藤沢市の方から年2回の内1回は法人協議会でやって欲しいと逆に言われるようになりました。市に視察にきた他市の方が「市の主催とか市社協がやるのでなく障がいの法人協議会があって、しかもそこが主催だっていうのはすごいね。やっぱり障がいが中心なんですね、藤沢は。」なんていう感想を持たれて帰ったなんて話を聞きました。
記念イベントの開催
本谷 協議会がスタートして20 周年ということで、12 月 2日イベントを開きまして、20 周年式典を藤沢駅前広場でやったんですね。サンパレットというところで。
記念式典をやるのに会場探しをするのが非常に難しく滞ってしまった。五十嵐代表から「やっぱり20 周年は今年やらなきゃいけないよ。」と言われたけど会場を探してもどこもない。それで市にサンパール広場の使用が可能か尋ねたらサンパレット広場という市民祭りやる場所なら良いと言われて実現しました。
式典に市長をはじめ市議会議長さんも来られたり、各団体の会長さん等20 人程来られました。30分間の式典に本当大勢の方が寒い中来ていただいた。式典が終わった後にイベントで、埼玉県で発達障害の方と職員の方が作詞したバンドを組んで、「猛毒ちんどん」っていう変わったネーミングで活動されているのを、テレビで見ましてね、お電話したら「いいよ。」ということで費用も安くやっていただきました。
サンパレット広場は通り道にもなるようなところなんですが、10 時半から16 時近くまで色んな方が見て下さいました。また、当事者が各法人からも自分の持ち味で参加したり、職員さんが各法人をアピールしたり、模擬店もあったり、そんな記念イベントを実施しました。市社協も協力しますと参加いただき、差別解消法のティッシュを500 個くらい配布していました。
それでは、五十嵐代表から今まで20 周年経過し、これからを考えると藤沢市の課題として当協議会がこれからどういうふうにするかという事を含めたお話をしていただければと思います。