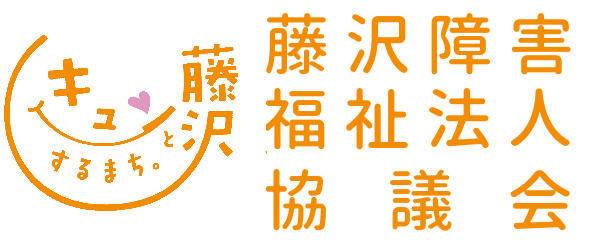藤沢障害福祉法人協議会のこれから
五十嵐 私は今は代表をしています。だけど協議会の代表もお互いに当番制でやりましょうっていう形になって、今度は戸髙さんに移ることははっきりわかってるし、自分が80 歳の節目に法人の40周年をやり、協議会の20 周年をやらせていただけた、数合わせじゃないけど、大きな節目の年になったなと思ってます。
そういう意味では私自身はもう終章に近くなっているけれど、もう出来上がっているので、これから次の世代の方たちがどう考え、どう進んでいってくれるのか、そこらへんのところは全部無限の期待感を持って託したいと思っています。
ただ1つだけ言えることは、今AIの進み方、IT関係の進み方についてもすごい加速度に速くなっている。だからこの10 年一昔と言ってたのが5年一昔、3年一昔って言い始めて、もうこれから10年という先のことはよほどの占い師でも当たらないんじゃないかと思っています。
やはり福祉業界は善人の集まり、それで「人間が人間を支援する業界だから結局AIなんか関係ない。」って言ってる人が現場で色々聞いてみると、とても多いです。そのことを私は危惧しています。そんなこと考えていたら、ただでさえ外国に日本は置いていかれているのに、その置いていかれている日本の中の福祉業界を担う、先進的にやってる藤沢市とは言いながらもそこらへんの所を私は心配しているところです。
なので、AIもつい最近の日経ビジネスの雑誌なんかも読んでると、今大手の会社では、1人の社員に1体のAIを秘書につけるんだって。そうやってわざわざ計算したりすることは全部AIに任せて仕事をやっていく時代。ますます拍車がかかって、ガサガサしてくる。
だからこそ逆に私としては「のんびり」「ゆっくり」というもう1つのキーワードで特徴を出していってもらいたい部分と、でも周りに追いかけられないようにAIに任せて済む問題は済ませていけるような交通整理をしてそれで利用者の人達がゆったりとのんびりと自分の個性に比較的合わせたような多様なニーズに応えていく。
昨日たまたま理事長巡視というのをやったんですけど、ケアセンターに行きましたら課長からの聞き取りで外からの声として、今うちがやってるやり方はあえて1人1人の性格やリズムに合わせながらいろんな支援をやっている。
そのことについて高齢者の施設なんかまだそうだと思うんですけど、「はい~の時間ね、健康体操の時間ね、こうやって~」って全員一緒にプログラムに追われることがとても苦しい、過ごしにくい。だけどここに来たらすごくゆったりのんびりやってくださっていて、光友会さんのデイサービスを気に入ってずっとやりたいって言っている方が何人か出てきているって言うのです。
なので、そういうところも大事にしながら、もう一方で代替できるものはAI等にやってもらって、支援の職員が利用者の人達に関わる時間を出来る限り多く作っていく。希望の郷のほうも大規模改修をしたので、お掃除をダスキンに出すことにしました。お掃除といっても日常的なものではなく、ベッドの下とか全部綺麗にする。それをお願いすることにしました。
それで昨日課長レベルの職員達に聞き取りをしたんですが、「どうですか? 少しは助かってますか?」というと、「大いに助かってます。」と。
これはAIではなく、人間がやってくれてるわけですけど、そういう様にできることは合理化して利用者の支援に対してもっと時間と専門性を発揮していく。そういうことを交通整理しながら今後は仕事にあたっていっていただければ良いのではないか。と、これは老婆心ながら具体的な事も加味した上で、後は全面的に若い方たちに頑張ってほしいと思っております。
本谷 はい、ありがとうございました。石渡先生からも今までの話から、これからも含めて当協議会に対して期待することとかどうでしょうか?
石渡 この協議会は障がいのある人の支援という所から始まって、地域をいろんな意味で変えてきているんだろうなと思うんですよね。
そういう時に「津久井やまゆり」の事件の話にもなっていくんですけど、あの事件が「なんで障がい者の支援者である植松がやってしまったのか?」という話になる時に、今の社会の矛盾みたいなものが見え隠れしていると思います。
さっき紀子先生が合理化できるところは合理化してきちんと支援というところに向き合うという、そういう向き合い方をしているところで、地域の色んな人達と関わっていってると思うので、そこで「人を大事にするとか命を守るのはどういうことかな。」という発信をし続けてほしいなと思います。やはり「小さい子どもがどういう風に藤沢で育っていくかっていうのが改めて大事になってくるな。」と思うので。
子どもの時から教育界の活動の中に巻き込むようなことを意識して、藤沢の地域福祉の計画に関わっていて、障がいは強い、高齢もそれなりに頑張っているところがある。でも、「子どものことがいつも藤沢ではちょっと弱いよね。」っていう話になって、子どものところで頑張っている人達もいるんだけど、そこが「ある部分での頑張り」であって、藤沢全体には広がっていないのかな。「聖園子どもの家」だとか色々子どもの法人もあるんだけど、藤沢の中で見えてこないところがあるなと思っています。
子どもの時からどう藤沢で育ってほしいかっていうところにももっと関わってもらうと良いかなと思いますが、今日色々お話を聞いてみてやっぱりスタートの時から作業所でっていうところが改めて大事だし、今ちょっと違うところにいるけどみんなそこで繋がってたんだみたいに感じて、やっぱり地域からスタートするというところがここの協議会の成果になってるんだなと思うし、そういう協議会の動きが重心協議会で準備会とかやるじゃないですか。
あの時に行政がしっかりデータを揃えてきてるなと思うことがあって、ああいう風に行政を動かしているのが、この協議会の活動だったりするんだなと本当に感じるんですね。行政も確実に育っているのは、市民の視点でいろんな人達とつながってこの協議会がやってきたのがいなって改めて思うので。
今藤沢でもう少し頑張ってもらわなきゃいけないというと、本当に大事な子どものところがまだなので、そこも含めて最後まで藤沢で安心して且つ、活き活きと自分らしく個性が輝くでしたっけ? あのキャッチフレーズも素晴らしいなと思うんですけど、もう30 年くらい前からやってますよね。
そこの教育が大事にしてきたところをさらに広げる、次の世代にとおっしゃったところと併せて、子どもの時からみたいなアプローチができると良いのかなと思っております。
本谷 はい、ありがとうございます。最後にこれからの協議会の使命ということで皆さんにお話していただければと思いますが。では齊藤さんから。
齊藤 そうですね、抜けてるところがやっぱり子どものお話があって昨日ちょうど鎌倉養護学校の評議委員会があって行ったんですけど、あそこはすぐとなりが門1つ隔てて関谷小学校っていうのがあって。小学校とすぐ繋がってるんですよ。
そことの交流の話の発表があって、そこでいい交流ができたと思って持って帰るお子さんもいれば、嫌だったというのもいたり、それは当然なんだけど。そういう出会いの場であるとか、触れ合いの場であるとか、知るきっかけというのかな。そこのところをもう少し外に向けてやっていくのが必要なのかなと感じますね。
私のマロニアなんか重心の方で非常にリスクの高い方が多いので、「どこでも行きましょう。」ってなかなか出来ないので、つい消極的にはなってしまうのですけど。まず知ってもらうっていう事がまだ足りてないような気がしますね。あちこちの会議なんか行っても、いろいろな専門分野で頑張ってる方々が集まってきているのだけど、重心に限らず、障がいのことってやっぱりわからない。
最近医療との接点を作ろうと思ってやってるんですけど、医療者から見ると障がいの事はわからないんですよ。小児科の先生はわかるんですけど、成人の先生たちは臓器1個1個しか見てないので、障がいという全体像がわからないんですよね。そこのところをどうやっていくのかなというのが、大きな課題かなと思っているのが最近です。
我々が当事者と知り合ってもらうのも大事だし、我々が専門家と思われているとすれば、専門家同士でしかわからない言葉で言ってしまってはやはり広がらないので、「いかに専門外の人に難しい話をわかりやすく話ができるか?」というのが我々の大きな役割なのかなと感じます。
本谷 戸髙さんどうですか?
戸髙 前に防災の関係で動いてる時にずっと課題だったのが、藤沢の13 地区の市民センターと、例えばその地区にある施設とどう関係をとるかということでした。マップを作りましたが、あれで終わってる感じがして、我々がどう発信していくかっていう時に身近なところから発信をしていくなどの仕掛けをしていかないとまずいんだろうなと。
それぞれの施設が地域の中でどんな展開をするか意識的にやっていく。本当は市民センターにいろんな仕掛けをするということでそこまでやったんだけど、その後の動きができてないですね。職員も自分の施設に来ている人達ばかりではなくて、少なくともその周辺とどうするか。
最近防災の関係で高齢の所ともやり取りをして、藤沢型もあるんでしょうけども、そういう連携を我々だけじゃないところの展開も次に考えていかないと、なかなか向こうもわかってくれない。素材はいっぱいあるんだろうなと。うまく展開すればできるところだし、例えばここの地区なんかですと、防災があった後にそういう仕掛けをしてそれなりに出来ている。やっぱりその仕掛け方はどこかの団体だけじゃなくて、法人協議会の話をしながら、「ちょっとそういう動きしようよ。」っていうのと、もっと広げていく必要があるかなという気がしていますね。
齊藤 防災なんかだとね、2年続けて滝の沢中学校の避難所立ち上げ訓練はうちが一緒にやっているんですよ。そうするとやっぱり避難所に行くっていうのはどうやって行くんですかって時にうちの送迎車を出したんですね、そうすると「あ、こういう車があるのか。」って、そこからして皆さんあまり知らないんですね。送迎の車が走り回ってるのは見てるけど、乗り降りしてる姿はあまり見てない。
初めて市の担当者の方も、市の計画では市の公用車を使って搬送するってなっているんですけど、市の公用車って軽トラと軽のバンしかないんですよ、それに初めて実物見て気がついたりっていう話があったりとか。我々が「当たり前だと思ってることすら知らないんだ」と逆の発見をしたんで、まだまだ足りないなと実感しました。
それがモデル地区になって全市に広げていこうってマニュアルみたいなのを作っていこうねって話になってるんですけど、今言ってたように仕掛けていかないと、待ってても誰も気が付かない。我々が改めて認識して動かなきゃいけないのかなと思いますね。
本谷 はい、では小林さん。
小林 先程の話から出て思ったのは、時代の流れの中で作業所が原点だっていうところで、作業所で始めて、福祉がサービスになって措置から契約へという形の時代を経て、また一巡して元のところに戻ってるかなって思います。昔ながらの人とのつながりみたいなところの一番の原点から始まって、それが段々専門分化されて、サービスの受けてと送り手というところでお金に換算されてってなったんだけど、そのシステムだけじゃまたどうにもならなくなってきた。で、国も地域共生社会の我が事まるごとって言い出しちゃったのはもうどうにもならないと。
こちらも金を要求するだけじゃどうにもならないっていうことがわかっているから、そうすると昔ながらの我々が作業所としてやってた一緒の仲間みたいなところにまた光が当たって、それをどうやって新しい形にしていくかっていうのが次の世代の法人の我々の職員に受け継いでいくことかなって思います。
さっきAIの話もありましたけど、五十嵐理事長おっしゃったように使えるところは使うべきだと思うんですよね。たぶんAIって知性や合理性な部分はできるんだけど、我々がやってる感情とか欲求とかいうところ、ヒューマンのところは我々人間同士にしか絶対できないから逆にそこに特化していけばいいわけでね。
みんなパソコンばっかりやる時代になったじゃないですか? あれだって逆に今そういう時代かもしれないけど、もう一回AIにやらせることになりますよね。PCにやるようにさせて、今までPCやってた連中は逆に関わりができるか? って言ったらちょっと怪しいぞっていう気がするので、そこは我々の出番かなと。
今しょうがないからこれやってるけど、本当はそうじゃないぞ。みたいなところをうまく伝えていくことが大事かなと。
戸髙 地域貢献とかいう話が出たけれど、もう一回「地域に対して自分達が何をどうするか?」っていうところを問われている状況なんだと思います。
小林 地域の縁側事業っていうと本当に面白いのは、地域の人って頼りになるなっていうか。場があるといろんなことをやってくれるし。おばあちゃんおじいちゃんもそうだし。
ここに来ると面白いと思ってくれる人がいる。私がいるというのもあって、結構障がいの人も来るんですよ。幼稚園の子と統合失調症のおにいちゃんがすごく仲良くなって。「ちゃん呼びあい」してるんですよね。30 いくつ、40 ちょいのと、年長さんの女の子。お互いちゃん呼びで、「~ちゃん今日くるの?」みたいな感じになってるのが面白いね。
幼稚園だから統合失調症もなにもわからないけども、あれがちょっと大きくなってくればだんだんわかってくるから、「あのおにいちゃんだったんだね。」とわかると思うんだけど、でも「良い人だ。」って絶対思うから。ああいうのが大事だなと思います。
自閉のおにいちゃんがその辺のママさんに話しかけたりして、そのへんがすごい面白い。お互いなにも言わないんだけど、でも話しかけられるほうもわかるじゃないですか、バリバリの自閉だから。でもね、普通に会話してるのね、面白いですよ。
本谷 はい。自分もお話聞きながら、縁側のことで言うと、光友会も喫茶室が今地域の縁側事業で、場所柄来てくださいって言っても来れませんから、市民センターに朝は月水金送迎してるんです。もうほぼ3年変わらず来てる方が5人くらいはいるんですよね。70 越えてる方たちで、そういう方が月水金何をやるのかもこちらから仕掛けをして、それを楽しみに来られている。毎月の予定を市民センターから各家庭に回覧として回しています。
そういう仕掛けをしながら、来てみたら、「ああ、また来よう。」っていう人が出てくるんですね。やっぱりそういうのは続けていくのはいいんだなって。3年続けてボランティアになる人もいますし、健康体操だとマイクロバスじゃないと乗りきれないくらい来ます。
今後またそれもこれからの難しさもあるとは思うんですが、今日お話聞きながら、使命というか、協議会としてどういうふうにするかなんてことでは、こういう運動体としての協議会は進んでいかなきゃいけないんだなと思います。
五十嵐理事長が言うようにどれだけ支援をしなきゃいけないか、人手はますます少なく、来ない。そういう中でどう自分達が動けるのか。社会の動きを察知して使えるものはそこで連携をとるとか、研究者とできるだけお互いに使えるものを出し合うとか。
やはり勉強しなきゃいけないと思いますよね。地域福祉っていうタイトルがありますが、僕らも岡 村重夫さんの『地域福祉論』なんていうのも全部読み込めてないんですが、勉強が必要だと思います。やっぱり地域がコミューンのように皆が共同できるか。閉じられた世界で、自分たちだけでやるん でなくて、地域が活性化してお互いの問題として戦後の親の問題が子に、これから親亡き後にどうするとか、そういうところも引き受けなければいけないんじゃないか。
障がいを持つ方が、精神の方なんかは子どもができるとやはり鬱になるとか、時代がそういう、自殺は減ったとは言いつつも、引きこもりとか、親が抱えなければいけないっていう人がもっと潜在化されているわけですし、藤沢の地域でどうできるか。
そこらへん協議会、僕なんか60 過ぎてますから、やはり若手がこの職場でそれぞれどのように自分たちが生きていく上での楽しみをどうするのか、そういうことをどれだけ伝えられるかなと、きちんと筋立てて、次のミッションがあったらなぁという想いなんですが。
あと一言ずつ何かあるようでしたらお願いします。
五十嵐 私が一言だけ言いたいのは、今石渡先生から指摘を受けた、確かに藤沢は子どもの問題が弱い。それで社協が事務局なってもらって考えている藤沢の地域貢献、その事業の出発に向けて検討委員会やっています。郡部さんも委員として一緒に出てくれているけど。
その中では子どもの相談センターの人達もきてくれてるし、聖園子どもの家の職員もきてくれている。だからそういう中でもう少し具体的な協議会としてこれから幹事会のほうでも色々話し合ってもらって、弱いところを強いようにできるようにそこらへんは1つ力を入れてやっていったら良いと思います。それだけは言っておきます。
齊藤 今までの流れとちょっと違うんですが、NPO法人えぽめいくを立ち上げたじゃないですか。あれの流れって藤沢ならではと思うんです。他の市で考えればね、大手の法人だとか社協とかになっちゃったりすると思うんだけど。
小林 障害福祉法人協議会の蓄積があったからね。
本谷 福祉人材確保と言うところで学生さんはどうなんですか。
石渡 学生はとにかく福祉希望者がいない。受験生が少ないし、福祉とか勉強しても、それこそ金融機関に行っちゃうとか福祉畑じゃないところに行っちゃう。実習とかボランティアに行って出会うと、学生は変わるし、人生を受け止めてちゃんとこう回ってるなっていうのは感じます。
今年初めてうちの学科で卒論発表会っていうのをやったんですよ。そしたら10 人発表して、4人くらいは発達障害とかを発表してるし、それから児童虐待だとかをやる子が2人くらいいたりとか、けっこう他の保育士さんの養成では出てこないところにしっかり関心持っていました。
大事なことを受け止めていってやって、発達障害の人の犯罪みたいな、「お、こんなのやってるのか」みたいに思うんですけど。「あれ?」って思った事をしっかり方向付けるような指導をやれば、学生は変わっていくんだろうなって感じますね。
齊藤 結局我々って僕なんか就職のつもりじゃなかったんですよ全然。
一般企業にいてそれなりに給料もらってたんだけど、「これ放っておけないでしょ。」って飛び込んじゃった世界がたまたまここだったんで、それで給料がそれなりの安いのだっていうのは後からついてきた話で、運動体に飛び込んじゃった意識で。
今いてくれてる職員には職場なんですよ、職場として確立したつもりで入ってきてる。だけど、その後が続かないのはやっぱり元々社会的地位が低いじゃないですか。今だに処遇改善とかって言って、すごく失礼なやり方だと思うんですよね。
そういう扱いされてるから誰も見向きもしないし、でも知ってしまえば皆気がつくんですよ。そこのところの接点も隔離されちゃってるという感じがする。本当に人間にしかできない、崇高なお仕事だと思ってる、それを知らないんだよね、皆ね。
本谷 学生さんが研究するっていうのも人間というのは何かとかね、自分が知りたいことをやるわけ。きっかけが福祉であれば入ってくれるかなと、まだまだそこが今言ったような給料の問題、やっぱり学生はそこ見ちゃうもんね。
齊藤 社会的地位を上げることで優秀な人材が来るっていう条件に変えていかなきゃダメだよね。
五十嵐 それは誰かが作ってくれる、お膳立てしてくれるものじゃなくて、我々がかつてそうしたように、自分がやらないと。「仲間をもう少し増やしてほしいよ。」と事業者に言う前に自分が行動を起こして呼んでくる。
以前、4大の新卒の人でちょっと足に障がいがある方がたまたま保育士の資格を持っていて、しいの実学園に応募してきて、だけど私面接ではっきり言ったんだけど、「あなたちょっとしいの実学園じゃ無理じゃない?」って。
体格の良い子もいるし、抱っこした時にあなたがよろけて怪我でもしちゃったら、子どももそうだし、自分もそうだし、そういうことを考えるとしいの実で仕事をしていくのじゃなくて、他の事業所でどうだろう? って話を持ちかけて。
結局は、今横浜のほうのグループホームのほうで支援員から始めて経験を積みながら、もちろん4大出ていろんな資格を持ってるから、社会福祉科ね、だから相談のほうの関係をやるようになったらそれこそできるようになるんだから、他より強くなるんだからって言ったらね、中学が村岡なんだけど、すごくイジメられたらしいの、そのことで。
だから嫌で嫌でしょうがなくて、わざわざ市外の女子校に行ったらしいの。私達のほうもあなたは障がいをお持ちなんで、「手帳も持ってらっしゃるでしょうから、障がい者雇用の枠で取りたい。」ってはっきり言ったの。
そしたら泣き出しちゃって。それが嫌でみんな逃げて回ってたんだけど、その現実を今度突きつけられて。それでそっちのほうもちゃんと見学に行ったりして本人が将来展望まで含めてやる気が出てきたら、もうすごく積極的に向こうからこっちにも連絡してくるようになったの。
だからその辺は意識を変えるっていうのは、なにがきっかけになるかわからない。そういうところでも1つのきっかけになったかもしれない。
郡部 人材確保のことでは、やはり私達現場の職員がこの仕事にやりがいを持って生き生きと働く姿を社会に見せていかないと周りからは「ああ、福祉ってどんなに大変なんだろう」と、いわゆる「5K」ということになってしまうという1つ反省があります。
あと子どもの話が出ましたけど、今社会福祉法人の地域公益の取り組みが義務化されていますよね。先ほど五十嵐さんのお話にもあった、地域公益事業推進協議会が、社協を中心として始まっていて、私もここの障害福祉法人協議会の2名枠の1名として出させていただいていますが、そこに「あすなろサポート」さんと「聖園子どもの家」さんが参加されていて、児童養護施設を出たあとの18 歳から20 歳までの、そこのいわゆる受け皿がまったくないという話をされるんです。だから出たけども、戻ってきてしまったり、行方不明になったり、女の子だと風俗のほうに行ってしまうとか色んな問題があって、そこが本当に困っているところと。
今藤沢が目指してる藤沢型地域包括ケアシステムっていうのは縦割りではなく、横の繋がりで繋いで繋いで全ての市民を包括的に支えていきましょうということだと思いますが、そういう意味ではこの地域公益事業検討会の中でも議論になりましたけど、いろんな分野の事業者が横に繋がっていこうと。相談を受けたときに、ここは自分の専門だけどそこは違うよねということがある訳です。
じゃあワンストップで相談を受けたところが全て解決しなければいけないのかというとそうではなくて、また、それをうちは違いますと他へ回すのではなくて、責任を持って専門へ繋げていく、どんどん繋いでいこうと今言われ始めています。それは例えば障害福祉法人協議会として子どもの問題をやっていくという発想ではなくて、繋がることによって我々法人協議会の底上げもする。
今までは障害が専門だったけども、子どものことも何かできる分野があるかもしれないと、そんなお互いの知恵の出し合いが今始まっています。地域貢献は社会福祉法人の責務だから仕方なくやらなきゃならないではなく、それを良い方向に展開していけたらいいかなと思っています。
齊藤 連携ってどこでもいつでも言われるんだけど、相談業務なんかも連携でやるじゃない? だけど、基幹なんかで打ち合わせとかやる時にだいたい困ってるのがどうにもならなくなるとみんな基幹に来る。
実際には個人のはやらない法人なんだけど受けざるをえないっていうんで、そういう時に連携っていうものがあればいいんだけど投げておしまいじゃないかっていう事業所が多すぎる。だから連携でつなぐ相手がわかったら投げちゃえばいいっていうやり方でやっていくともう連携は壊れるからね。そこをちゃんと連携の仕方をちゃんと勉強しないとダメだと思う。
郡部 そこを社協がバックアップすると言ってくれています。公的な機関が責任を持ってくれないと民間はなかなか踏み出せない。相談窓口担当者のスキルアップも議論されています。
五十嵐 行政との関係で言えば、要求、要望だけでは駄目なんですよね、やっぱり提案型でいかないと。
齊藤 我々皆現場があって、現場の背景には全部当事者がいっぱいて、その人達の代弁者みたいな形でちゃんと事が語れてるんだと思うんだよね。事業所の利益とかじゃなくて。
五十嵐 でも国レベルの役人さんがよく言う事は、事業者が来ても駄目ですと。要するに事業所の利益を追求する人達が来ても受け入れられないという事だと思います。
だから当事者団体が行くしかないわけで、国会の周りを取り囲む重度の人達も大変なんだけど。
ところで、藤沢市は全国都道府県の市のうち住みたい街の第1位になったそうなんだけど、それは誰が対象かって言ったら、「子育てをしている主婦」だそうです。それが全国1位。
だけど今昨今の南口再開発の話、子どもの話、そういうところに湘南という環境が東京にも通学できる距離だし、藤沢はこれからすごく変わるから、変わった時に我が事まるごとがどうなるのか。我が事じゃなくて、他人事になっていったら困る訳です。
街の形が我々の仕事の形も変えていくことがあるからやっぱり見逃さないで注視していなくてはいけないと思います。
ということで、今日は大変ありがとうございました。
石渡 藤沢には長く関わってるから結構知ってると思っていましたけど、こういう事がいろいろあったんだって知ることができて、本当にありがとうございました。
郡部 本日はお忙しい中ありがとうございました。これで、藤沢障害福祉法人協議会創設20 周年記念座談会を終了いたします。